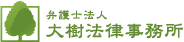2025.10.09
交通事故・保険
訴訟との関係における自賠責保険金の支払基準について

1 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故によって負傷または死亡した被害者を救済するために、全ての自動車に対して加入が義務づけられている強制保険です。
自賠責保険には、大量に発生する交通事故事案を、公正・迅速に処理して被害者を救済する要請があることから、訴訟において裁判官が認定する法的な損害賠償額とは異なる内容での支払基準(※)が定められています。
この支払基準は、交通事故被害者を救済するために、過失相殺や因果関係の考え方について、訴訟において下される判断よりも被害者に有利な運用を行っている一方で、認定する損害額自体は比較的低廉に抑えられているという側面もあります。
ただ、この支払基準は、自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」といいます。)によって法定化された基準であるものの、訴訟外で通用している基準であることに注意する必要があります。訴訟が係属すると、裁判所は自賠責保険の同基準に拘束されない判断を行い、自賠責保険による支払金額も、裁判所による司法判断を優先させた内容となります。
これにより、訴訟を行うことが、自賠責保険との関係で有利になることも不利になることもあるため、訴訟提起の判断・時期について適切な見極めが必要となってきます。

2 例えば、交通事故の加害者が任意保険に加入しておらず、その資力も乏しい場合でも、自賠責保険を被告として訴訟提起することで、自賠責保険の支払基準を超えた内容で損害賠償金を受け取ることができる場合もあります。
交通事故の被害者は、自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて、加害者が加入する自賠責保険会社に対して、保険金額の限度において損害賠償額の支払請求を行うことができます(交通事故の実務では、「被害者請求」と呼称される請求です)。
最高裁は、平成18年3月30日第一小法廷判決において、自賠責の支払基準は、「保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合に従うべき基準にすぎないものというべきである…訴訟においては、当事者の主張立証に基づく個別的な事案ごとの結果の妥当性が尊重されるべきである」として、被害者請求の訴訟においては、裁判所は自賠責の支払基準によることなく損害賠償額を算定できることを明らかにしました。
これによって、自賠責保険を被告として訴訟を提起することで、自賠責保険の支払基準を超えた内容の損害額が認定されて、自賠責保険からその支払いを受けることが可能となるケースも想定されることになりました。
もっとも、保険である以上、支払額は保険金額(傷害の場合は120万円)が上限となり、過失相殺も裁判所の認定どおりに反映されてしまうため、上記の方法が有効になるケースは、なお限定的といえます。

3 また、加害者が自賠責保険にすら加入していない場合や、加害者不明の場合には、自賠法に基づき、国が運営する政府保障事業が、自賠責保険とほぼ同じ機能を果たすことになります。
その場合にも、上記のケースと同じように、国を被告として訴訟提起することで、裁判所が政府保障事業の支払基準を超えた内容の損害額が認定して、国からその支払いを受けることが可能となる場合も考えられます(そのような裁判例として、京都地方裁判所令和3年6月4日判決などがあります)。

4 以上のように、交通事故の事案においては、自賠責保険等の制度や運用を十分に理解したうえで、適切な方針を選択することが重要となります。専門的な判断を要する場面も少なくありませんので、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
※:自動車損害賠償保障法16条の3により、国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準