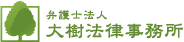2025.04.25
離婚・相続・遺言
親権・養育費などに関する民法等の改正について(令和8年5月までに施行予定)
1 はじめに

離婚に際しては、夫婦間において、財産分与や慰謝料、年金分割などの取扱いに関して協議が必要となりますが、お子さんがおられるご家庭では、父母の立場で、子の親権や養育費、親子交流(面会交流)に関しても十分に話し合う必要があります。
父母が、離婚後も、適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要と考えられており、離婚後のこどもの利益を確保することを目的に、令和6年5月、親権、養育費などに関する民法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(本改正法は、令和8年5月までに施行される予定となっています。)。
そこで、今回は、こうした父母の離婚後の子の養育に関する法改正のうち、実務上、大きな影響があると思われるルールの変更を、いくつかご紹介します。
2 親権・監護に関するルールの変更・見直し

⑴ まず、離婚後、父母双方を親権者として定めることができるようになりました(改正民法819条など)。
これまでは、父母の一方を親権者としなければならないとされていましたので、「共同親権」の選択肢が導入されたことは、大きな制度変更となります。
今後は、父母の協議により、父母双方、あるいは、父又は母の一方を、こどもの親権者として指定し、また、そうした協議が難しいような場合には、「子の利益」という観点から、裁判所が上記いずれかの方法によって親権者を指定することになります。
もっとも、例えば、子への虐待や父母間のDVなど、「父母の双方を親権者とすることにより子の利益を害する」ような場合には、単独親権としなければならないというルールも併せて規定されています。
いずれにしても、子の利益のため、子の心身の健全な発達にとって最善の方法が選択される必要があります。
⑵ また、婚姻中も含め、父母の親権行使に関するルールが規定されました(改正民法824条の2など)。
すなわち、父母双方が親権者である場合には、親権の共同行使が原則となりますが、「子の利益のため急迫の事情があるとき」や「監護及び教育に関する日常の行為」に関しては、単独での親権行使が可能とされています。
実際には、個別具体的な事情によるところも大きいと思われますが、法務省によれば、「子の利益のため急迫の事情がある」場合として、DVや虐待からの避難、緊急的な医療受診、入学手続など、「監護及び教育に関する日常の行為」として、食事や服装の決定、通常のワクチン接種、習い事、高校生の放課後のアルバイト許可などが例として示されています。
他方で、法務省によれば、こどもの転居、進路・進学先の決定、預金口座開設等の財産管理などは上記「日常の行為」に該当せず、共同親権行使の対象として説明されています。
このような特定事項に係る親権の行使に関して父母の意見が対立し、協議が難しいような場合には、裁判所において当該事項について父母の一方を親権行使者として指定する手続も新設されています。
3 養育費に関するルールの変更・見直し

⑴ まず、離婚に際して、養育費の取り決めをしていなかった父母間でも、一定額の「法定養育費」を請求することが可能になりました(改正民法766条の3など)。
この法定養育費の金額は、「子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算出した額」とされており、現時点で具体的な金額は明らかになっていませんが、改正前は、父母間の協議や裁判所の手続によって「具体的な養育費」を取り決める必要がありましたので、着目すべき制度変更と考えられます。
⑵ また、上記法定養育費や父母間の取決めに基づく養育費等の支払請求権について、「先取特権」という優先権が付与されることになりました(改正民法306条、308条の2など)。
これに伴い、今後は、これまで養育費の支払を怠った相手方(別居親)の財産を差押えるために必要とされていた公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」(及びその取得手続)がなくても、例えば、養育費等の支払に関して父母間で作成した離婚合意書などの文書を「担保権の存在を証する文書」として提出することで、差押え(強制執行)手続の申立てが可能になりました。
担保権として、他の一般債権者に優先して支払を受けられる権利も付与されています。
その上で、こうした先取特権の対象となる債権については、「子の監護に要する相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金より扶養を受ける子の数に応じて法務省令で定めるところにより算出した額)」とされていますが、現時点で具体的な金額は明らかになっていません。
この点、例えば、父母間で取り決めた養育費等の金額が、「法務省令が定めるところにより算出した額」を超えるような場合には、先取特権(優先権)の対象は合意した養育費等の金額の一部に限定されるものと思われますが、養育費の支払を確保し、こどもの心身の健全な発達を図るという観点からすれば、一定の養育費に先取特権(優先権)が付与される意義は大きいと考えられます。
4 結びに代えて

今回の法改正では、「親権は、子の利益のために行使すること」に加えて、父母が、「子の心身の健全な発達を図るため、子の人格を尊重すること」「婚姻関係の有無にかかわらず、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力すること」など、父母が子に対して負う責務についても併せて明記されています(改正民法818条1項、817条の12)。
このように、離婚に際しては、父母が、こどもの利益という観点から、十分に話し合い、離婚後も相互に協力し合える関係性を構築していくことが望ましいところですが、現実には、離婚事件の性質上、父母間で協議を行うこと自体が困難なケースも少なくないように思います。
弊所では、今回取り上げた親権や養育費を含め、離婚や離婚後の子の養育をめぐる問題に関しても幅広く取り扱っておりますので、ご不明な点やお困り事などございましたら、お気軽にご相談ください。
※本記事は、令和7年1月時点の情報をもとに作成しております。