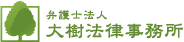2025.05.22
中堅・中小企業の法務支援
フリーランスとの契約で気をつけるべきポイント
近年、フリーランスと業務委託契約を結ぶ企業が増えています。
しかし、契約の不備が原因でトラブルが発生することも少なくありません。
2024年11月1日施行の「フリーランス・事業者間取引適正化等法」により、取引ルールが明確化されました。
本記事では、中小企業が気をつけるべきポイントを解説します。
1.書面等による取引条件の明示

フリーランスとの契約においては、書面または電子記録(メール・PDF等)により以下の取引条件を明示することが義務付けられています。
①給付の内容
②報酬の額
③支払期日
④業務委託事業者・フリーランスの名称
⑤業務委託をした日
⑥給付を受領する日・役務の提供を受ける日
⑦給付を受領する場所・役務の提供を受ける場所
⑧(検査をする場合)検査完了日
⑨(現金手段で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関する諸条件
2.報酬の適正な支払い

フリーランスとの契約において、委託した商品等を受領した日から起算して60日以内のできるだけ早い日を報酬の支払期日と定め、実際にその期日までに報酬を支払う必要があります。
但し、フリーランスに業務を委託した事業者が、元請から委託を受けた業務をフリーランスに再委託する場合には、一定の要件を満たせば、元請との間で定められた支払期日から起算して30日以内にフリーランスに支払うよう定めることができます。
3.不当な契約変更等の禁止

フリーランスに1か月以上の期間行う業務を委託している場合、下記の行為が禁止されます。
・フリーランスの責任ではない理由での受領拒否
・フリーランスの責任ではない理由での報酬の減額
・フリーランスの責任ではない理由での返品
・買いたたき
・正当な理由がない場合における指定商品の購入強制や、指定役務の利用強制
・不当な経済上の利益の提供要請
・不当なやり直しや給付内容の変更
また、6か月以上の業務をフリーランスに委託している場合、事業者がこの契約を解除するためには、少なくとも30日以前に、書面や電子メール等により解除の予告を行う必要があります。
解除予告の日から解除日までに、フリーランスから契約解除の理由の開示を求められた場合、事業者はその理由を開示する必要があります。
4.ハラスメント対策

ハラスメント行為によりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、事業者はフリーランスからの相談に応じ、適切に対応をするため体制整備やその他必要な措置をとる必要があります。
事業者がとるべき措置として、以下のようなものが考えられます。
・従業員に対するハラスメント防止のための研修の実施
・フリーランスが利用できる相談窓口の設置や相談担当者の指定
・ハラスメントが発覚した場合の調査体制の構築
なお、「納期遅れ時に威圧的な発言をする」「契約外業務を強要する」などの行為はパワハラに、「個人的な接触を求める」「性的な発言を繰り返す」などの行為はセクハラに該当する恐れがあります。
このような行為が行われると、当該行為を行った従業員だけでなく、事業者も法的責任を問われることになります。
5.育児介護等と業務の両立への配慮

フリーランスに1か月以上の期間行う業務を委託している場合、フリーランスからの申出に応じて、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう配慮する必要があります。
6.法律の専門家に相談を

フリーランスとの契約に不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、中小企業向けにフリーランス契約のチェックやトラブル防止のサポートを行っています。
適正な契約を結び、安全な取引環境を整えるために、お気軽にご相談ください。