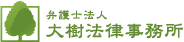2025.02.18
刑事事件
冤罪事件の当事者にならないために~当番弁護士制度等~
1 日常に潜む冤罪のリスク

令和6年9月26日、袴田事件で無罪判決が下されたニュースは、多くの方の記憶に新しいことでしょう。袴田さんは昭和41年8月18日に逮捕されて、昭和55年11月19日に死刑判決が確定し、その後獄中で長い年月を過ごし、自由を取り戻すまでに58年もの歳月を要しました。その間に失われた普通の人生や時間の重みを考えると、冤罪の恐ろしさを改めて実感します。そして、このような出来事は決して他人事ではありません。
現代では、一部の事件に関しては取調べの録音・録画が義務付けされる等、捜査の適正化が進んでいます。しかし、例えば満員電車で痴漢の疑いをかけられただけで、無実であっても何日も勾留される可能性があります。たとえ嫌疑が晴れても、会社を長期欠勤したことで解雇されたり、噂が立って家庭が崩壊したりするかもしれません。
「自分は冤罪の当事者にはならない」と思う方が多いでしょう。しかし、痴漢のような犯罪を許さないことは当然としても、不当な嫌疑をかけられるリスクがゼロではないことを意識しておく必要があります。
2 当番弁護士制度の活用を知る
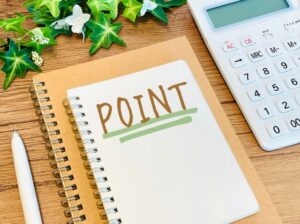
万が一、警察や検察に疑われ逮捕されてしまった場合、どうすればよいのでしょうか?このような時に頼れるのが「当番弁護士制度」です。
当番弁護士制度は、逮捕された人やその家族が依頼できる制度です。警察官や検察官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えるだけで、弁護士が無料で1回限りですが、面会に来て相談に応じてくれます。
逮捕されると、多くの人が「いつまで勾留されるのか」「弁護士を頼むべきか」「取調べで正直に話した方がいいのか」など、様々な不安に襲われます。弁護士との面会時には、警察、検察からの取調べに対してどのように対処したらよいか、黙秘権の保障など、自らの身を守るために必要な様々な事柄を率直に相談することができます。
そして、弁護士との面会は警察官の立会いがなく行われるため、安心して相談できます。
3 弁護士への早期の依頼の重要性

当番弁護士制度は、冤罪のリスクを軽減するための重要な初動対応です。逮捕された場合は、まず弁護士に相談し、警察の取調べへの対応方法や今後の方針等を相談することができます。
冤罪事件や誤認逮捕、刑事トラブルに巻き込まれることは誰にでも起こり得るものです。だからこそ、突然の事態に備え、当番弁護士制度について覚えておいていただければと思います。
4 被疑者国選弁護制度について

最後に被疑者国選弁護制度について、少し説明を加えたいと思います。
被疑者国選弁護制度は、被疑者が勾留されてから、勾留された被疑者の経済状況等により弁護士費用を負担することが難しい場合、本人の請求等により、裁判官が弁護人を選任する制度です。以前は国選弁護制度の対象を被告人のみであったものを被疑者にまで広げたものです。この制度も、できるだけ早い段階で弁護人に面談できるという点で重要な制度です。
冤罪事件の当事者にならないためにという観点からは、被疑者国選弁護制度についても、当番弁護士制度と共にこの機会に心に留めていいただくと良いと思います。